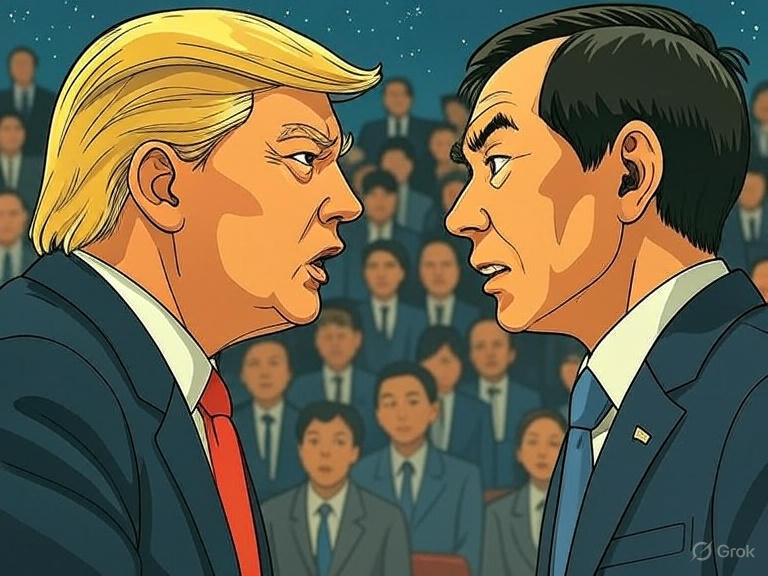2025年9月18日(日本時間)に行われた、米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策金利は、0.25%(25BP)の利下げで、市場の予想通りの結果となりました。
この記事では、「金利とインフレとデフレ」、「為替と株と仮想通貨の関係」を、実際の現在の経済状況に合わせて、分かりやすく解説しています。
この記事を読むと、それぞれがどの様に相関しているのかが分かります。
FOMCが揺るがす世界経済
2025年9月18日深夜1時(日本時間)、世界中の市場は米連邦公開市場委員会(FOMC)の決定を固唾を飲んで待っています。(この記事の執筆はMOMCの発表1時間前に執筆)
会合は9/16–17(米東部)、声明は17日14:00 ET=日本時間9/18 03:00
市場は25bp(0.25%)の利下げを96%以上の確率(CME FedWatchベース)で織り込み済みです。
→結果は市場の予想通り0.25%(25BP)の利下げ
一方、ドナルド・トランプ大統領の声が再び響き、FRB議長のジェローム・パウエル氏に「利下げを急げ」と圧力をかけています。
日本銀行(日銀)も9月18-19日の会合で据え置きが予想される中、金利差が為替やインフレに与える影響が焦点です。
トランプの利下げ要求:経済活性化か、インフレの火種か?
トランプ大統領の主張は変わらずシンプル。パウエル議長の利下げ遅れを非難し、「今すぐ下げろ」と迫っています。
狙いは低金利による企業借入促進で、投資・雇用をブーストし、経済成長を加速させること。
FOMC発表直前の9月18日時点で、ダウ平均は300ポイント上昇するなど、リスクオンムードが広がっています。しかし、利下げの裏側にはインフレ再燃のリスクが潜みます。
金利低下は通貨供給を増やし、お金の価値を下げるため、物価上昇を招きやすい。米経済はインフレが2%目標に近づきつつありますが、25bpの小幅利下げでも過度な緩和は避けたいところ。
トランプ氏の政治的介入がFRBの独立性を脅かす懸念もあり、結果としてドル安が進む可能性が高いです。この連鎖は、グローバル貿易や仮想通貨の投機需要に波及し、経済の「ドミノ効果」を加速させる可能性が高いとの見方が強いです。
また、利下げ期待が高まる中、長期金利の上昇が市場の信頼を損ない、Fed(米連邦準備制度)のコントロール喪失を招くベアリッシュな影響も懸念されています。
さらに、利下げの影響を考える上で、国債利回りの変化が鍵となります。
利下げにより国債利回りが低下すると国債の購買力が弱まり、そうなると米ドルが買われなくなり、通貨安(ドル安)を誘発します。
しかし、アメリカは企業の景気が良く株が買われやすいので、米ドルの価値が落ちにくい構造です。
さらなる利下げでも、実態経済が堅調であれば米国株への投資が増え、世界中の投資家がドル資産を求める流れが生まれます。
結果、ドル需要が高まり、結局ドルは強含みとなります。この「実態経済の強さ」が、利下げの通貨安圧力を相殺するメカニズムです。
インフレと利下げのジレンマ:アメリカ vs. 日本
アメリカでは、インフレ抑制が利下げの鍵。
FRBは労働市場の弱さとインフレの軟化を背景に、25bp利下げをほぼ確実視していますが、ジャンボカット(50bp)の確率はわずか4%。
長期金利は9月18日時点で10年債利回りが「4.03–4.05%」のレンジ高止まりで、給与水準の高さが物価耐性を支えています。一方、日本は長年のゼロ金利政策でデフレが慢性化しましたが、賃上げの兆しと輸入インフレで状況が変わりつつあります。
デフレマインドの原因は消費者の将来不安による貯蓄志向、生産性低迷、過去の円高圧力でした。
ここで、アメリカと日本の賃金格差を比較すると、その差がインフレ耐性の違いを如実に示します。
2025年8月時点のデータでは、アメリカの平均時給は約31.46米ドル(約4,700円)と高水準。
一方、日本は派遣労働者の平均時給が約1,622円(約11.38米ドル)と推定され、全体平均時給も約2,000円(約14米ドル)程度です。
つまり、アメリカの時給は日本の2倍以上で、年収換算でもアメリカの平均約6万ドルに対し、日本は約3.7万ドルと半分以下。この格差は、生産性や労働市場の競争力の違いから生まれています。
なぜアメリカは賃金が高いからインフレに耐性があるのか?
それは、賃金上昇が物価高を「吸収」しやすいからです。高賃金は消費者の購買力を維持し、インフレが起きても生活水準の低下を防ぎます。
例えば、食料や住宅の価格が10%上がっても、賃金が5%上昇していれば実質負担は軽減されます。
アメリカでは、サービス業中心の経済で賃金が物価を押し上げる好循環が生まれ、FRBの利下げ余地を広げています。
これに対し、日本は低賃金が消費を抑制し、デフレを長引かせてきましたが、最近の春闘で賃上げ率が5%超と過去最高を更新。
2025年上期の有効求人倍率1.3倍超も、労働需給の逼迫を後押ししています。
今、日銀は9月18-19日の会合で政策金利を0.5%に据え置きが予想されますが、Q4(10-12月)に25bp以上の利上げの可能性を多数のエコノミストが見込んでいます。
目的は円安抑制とインフレのソフトランディングですが、消費減速のリスクが伴います。
特に中小企業は借入金利上昇で打撃を受け、給与転嫁が難しくなる恐れ。
株価は輸出大手が支えていますが、全体経済の鈍化を招く可能性もあります。
日銀の慎重姿勢は、米利下げとの金利差縮小を意識したものです。
この利上げ可能性の根拠は、賃金上昇とインフレ抑制の好循環にあります。
2025年の賃上げが定着すれば、消費が活性化し、インフレ率を2%前後で安定させられます。
低賃金時代はインフレが消費を圧迫し利上げを躊躇わせましたが、今は賃金がインフレの「クッション」となり、過熱を防ぎつつ成長を支える基盤ができています。
日銀はこれを「賃金・物価の好循環の確立」と位置づけ、利上げのトリガーとして活用。
結果、インフレを抑制しつつ経済を正常化する余地が生まれています。
為替の行方:円高圧力とドルの粘り強さ
米利下げと日銀の据え置き(潜在的な利上げ示唆)は、金利差縮小で明確に円高を誘導します。
9月18日時点のドル円レートは147円前後(直近高値147.96円、低値146.35円)と円安基調ですが、FOMC後のドル安で140円台後半へのシフトが予想されます。
100円台のような極端な円高は現実的ではなく、市場は金利差(米4.03% vs. 日1.60%)の残存を考慮。
25bp利下げでも差は3%以上残るため、即時崩壊は避けられそうです。
日本にとっては輸入コスト低下のメリットですが、輸出企業には逆風。
トランプ氏の「日本は通貨安で輸出有利」との批判も、貿易摩擦の火種となり、金利・為替の連鎖を複雑化させています。
一方では、「日銀の政策が低金利を維持すれば円安が続き、キャリートレードの復活を招く可能性が高い。」といった声も見られます。
この逆風の具体例として、自動車輸出を挙げましょう。
1ドル=150円の円安時、150万円の日本車はアメリカでちょうど10,000ドルで販売可能。
価格競争力が保たれ、売れ行きが好調です。
しかし、1ドル=100円の円高になると、同じ150万円の車が15,000ドルに跳ね上がり、アメリカ市場での価格が割高に。
結果、日本製品の競争力が失われ、輸出量が減少し、企業収益を圧迫します。
このように、円高は輸出依存の日本経済に打撃を与え、日銀の利上げペースを慎重にさせる要因となります。
トランプ関税の影:実行加速、市場は警戒
トランプ大統領の関税政策は2025年に入り本格化。
中国への10%関税が2月から発動され、追加で20%引き上げの執行命令が出されています。
日本向けも相互関税の枠組みで脅威ですが、9月5日のホワイトハウス発表では90日延長の猶予を与え、即時影響は限定的。
第一期政権のように自国産業保護を狙いますが、共和党内や企業(NVIDIAなど)の反対で調整中。
現状、iPhone 17 Proの価格が1,199ドルと据え置きで、関税の直接影響は未反映。
中国製品への追加関税脅しは株価を揺るがせ、地政学リスクが市場ボラティリティを高めています。
この政策はインフレを押し上げ、FRBの利下げ余地を狭め、為替変動を助長する可能性大です。
一方で、トランプの関税が雇用を42,000件失わせ、製造業を衰退させ、経済全体をパンデミック以来の不況に追い込んでいる。 また、関税がアメリカのGDPを0.4%縮小させ、年間1,500億ドルの損失を生むとの指摘も。
仮想通貨への波及:リスクオンとトランプのビットコイン支持
金利低下の利下げ期待は、仮想通貨市場に明確なリスクオン効果をもたらします。低金利環境は投機資金を呼び込み、ビットコイン(BTC)を「デジタルゴールド」として買わせやすいのです。
9月18日時点でBTC価格は116,000ドル前後と堅調で、FOMC後の120,000ドル超えを市場が期待。
利下げ織り込み済みの過熱感はあるものの、ETF流入の回復と機関投資家の蓄積(SMI上昇)がセンチメントを支えています。この流れは、米経済の安定(株高・雇用堅調)と連動し、インフレ抑制の成功がBTCの長期上昇を後押しする構図です。
一方では、トランプのBTC支持が政治的圧力によるもので、実際の市場成長を伴わず、関連ミームコインの停滞を招いているとの指摘もあります。
さらに、トランプ大統領のビットコイン支持が追い風。
2025年3月の大統領令で「Strategic Bitcoin Reserve(SBR)」を設立し、政府保有の没収コイン(税金不使用)で運用開始。議会で法案推進が進み、マイケル・セイラー氏ら業界幹部がロビイング中です。
これにより、BTCは国家戦略資産として位置づけられ、利下げによるドル安が仮想通貨の相対価値を高める連鎖を生んでいます。
日本ではSBI証券のRWA(リアルワールドアセット)活用やQR決済のグローバル化がブロックチェーン採用を加速し、か海外仮想通貨取引所itgetでは既にRWA(リアルワールドアセット)取り扱いが始まっています。BTCの2100万枚上限はインフレ耐性が高く、アルトコインの希少性問題を上回る強みを発揮しています。

結論:不確実性の時代をどう生き抜くか
2025年9月18日(日本時間)に開催されたFOMCでは、25bp(-0.25%)の利下げが行われました。
今後は、トランプの関税加速、日銀のQ4利上げ示唆がインフレ・為替・貿易の連鎖を加速させる可能性が示唆されています。
短期ではドル安・円高(147円→140円台)・BTC高(116k→120k)のシナリオが濃厚ですが、中長期では政治リスク(トランプ支持率40%以下に低下)が鍵となります。
投資家は金利差の変動を注視し、多角的なポートフォリオを。仮想通貨はリスクオンと政策支持で恩恵大ですが、過熱調整に注意。
日本経済の安定化は歓迎ですが、中小企業への配慮が急務です。FOMC後は市場反応をウォッチし、柔軟な戦略を立てましょう。
経済は予測不能ですが、チャンスも潜んでいます。
(参考:市場データは2025年9月18日午前1時時点の推定値。賃金データは米国労働省・日本厚生労働省2025年最新値に基づく。投資は自己責任で。)
最後までお読みいただきありがとうございました。